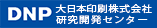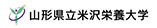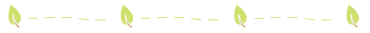Support system 支援制度
交換留学プログラム
平成27年度実施概要
異なる環境・文化を有している女性研究者と接することで、不安や課題を普段とは異なる視点で直に感じ取ることにより、女性研究者にとっての
阻害要因を互いにみつけ、それらを共に改善することでワーク・ライフ・バランスを保ち、そして成長し続けていける環境づくりを図ることを
目的としたプログラムです。
実施日時: 2016年2月11日(木)~13日(土)の2泊3日
参 加 者: 大日本印刷株式会社研究開発センターの女性研究者2名(山下かおり、桑原尚子)
訪 問 先: 山形大学農学部(鶴岡市)、山形大学工学部(米沢市)、米沢栄養大学(米沢市)

【主な内容】
①山形大学農学部 木村直子教授研究室の見学
動物機能調節学が専門で哺乳類卵母細胞の減数分裂機構、家禽類の生命工学技術の開発に携わっている山形大学農学部(鶴岡市)の木村直子教授
の研究室を訪問しました。研究室についてのひと通りの説明後、2名の女子学生による卵母細胞を用いた実験の様子を見学し、実験の目的や原理など
の説明がありました。
異分野の研究者に研究内容を正確に伝えるということは大切であるものの、実際には容易なことではありませんが、学生達はそれが充分に出来てい
ました。学部生にその能力が備わっていることに非常に感心し、木村教授の指導力の高さを実感しました。
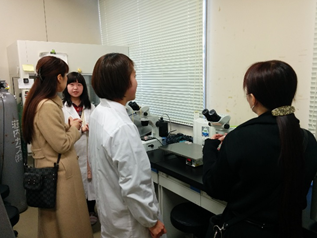

|
▲木村教授研究室の見学の様子 ▲集合写真 |
②山形大学工学部副部長・男女共同参画推進担当 落合文吾教授との懇談
山形大学工学部(米沢市)を訪れ、工学部副部長 落合文吾教授から山形大学の特徴についての話があった後、ダイバーシティ研究環境実現イニ
シアティブ事業の取組のひとつである大日本印刷株式会社主催の『共創ワークショップ(サービスデザインプロジェクト)』の平成28年4月以降の
活動について意見を交わしました。落合教授は、サービスデザイン思考に関する関心が非常に高く、予定の1時間を大幅に超える1時間半の懇談とな
りました。
③重要文化財 旧米澤高等工業学校本館の見学
山形大学工学部同窓会、一般社団法人米澤工業会理事長、山崎洋一郎氏の案内で山形大学工学部の敷地内にある旧米澤高等工業学校本館を見学しま
した。米澤高等工業学校は、日本で7番目の高等工業学校として1910年3月に開設、学制改革によって山形大学工学部となりました。1973年に国の
重要文化財に指定、2000年に創立90周年を迎え、現在は創立90周年記念展示館として多くの歴史的資料を展示しています。

|
▲旧米澤高等工業学校 |
④山形大学工学部 黒谷玲子准教授研究室の見学
分子生物(遺伝子工学)、生理学の専門で呼吸器疾患を治す新薬の開発に携わっている山形大学工学部の黒谷玲子准教授の研究室を訪問しました。
メンターとなるべき女性研究者を求めて海外の女性研究者3名に師事を仰いだという黒谷准教授話を聞き、『自分のやりたい研究をやるためには自分
の道は自分で切り開く』という不屈の精神を学びました。また、先生の『研究が好き』という気持ちに支えられて、大変なことも乗り越えてきたとい
う話に共感しました。正に研究者にとって『研究が好き』であることは研究者を続けるうえでの必須条件のひとつでると思います。
しかしながら、”企業の”研究者は、利益追求も考えなければならず、好きという感情が薄れてしまう研究者も多いという現状を考え、女性研究者を
増やすためにも、好きという思いをなくさないような取組を実施していきたいと感じました。
⑤山形県立米沢栄養大学訪問
国家資格である管理栄養士を養成する山形県唯一の大学である米沢栄養大学を訪問しました。米沢栄養大学では、保健、医療、福祉、教育などの
場において、県民の健康で豊かな暮らしの実現に寄与できる栄養に関する高度な専門知識と技術を身につけた人材の育成を行っています。
まずは、健康栄養学部健康栄養学科長 鈴木一憲教授から大学についての全般的な話明を受けました。山形県は塩分の摂取量が47都道府県中で
2番目に多く、高血圧患者数はワースト1であるという調査結果を受け、この事態を改善するために山形県では食育に力を入れています。そのため、
県や市より米沢栄養大学に共同研究の依頼が多数寄せられるとのことでした。地域に根ざした研究を行っているということが、この大学の特徴の
ひとつであると感じました。『私は~のプロフェッショナルであり、誰にも負けない』といえること、これも研究者として成長し続ける要件である
ことを再認識させられました。

|
▲山形県立米沢栄養大学 外観写真 |
鈴木教授の説明の後には、江口智美助教より高齢者向け食品の物性・咀嚼生・指向性、ゲル状食品・含泡食品のテクスチャ(食感)制御をテーマとし
た研究概要の説明がありました。(図1参照)

|
▲図1 江口知美助教 研究テーマ説明図 |
早坂美希助手からは、山形大学医学部が行っている山形県コホート研究で得られた特定健康診査と食事パターンと疾病の発症の関連についての研究
概要の説明がありました。
研究概要の説明の後には、江口助教、早坂助手と留学生2名で女性研究者のみの意見交換を行いました。大学から支給される研究費は決して多くない
ため、外部資金(助成金)を獲得しなければならないが、ワーク・ライフ・バランスを考えると長期プロジェクトへの参加は女性研究者にとっては
躊躇われる場合があるという意見がありました。女性研究者を増やすためには、このジレンマを解消するような仕組みを構築しなければならないと
感じました。
最後には、充実した調理施設を見学しました。中でも給食業務の流れや大量調理の方法と技術、衛生管理を学ぶことのできる調理施設は素晴らしい
設備でした。

|
▲米沢栄養大学の調理設備 |
 2.女子学生が企業へ
2.女子学生が企業へ
企業に籍を置く女性研究者の研究に対する姿勢とそれを取り巻く環境を女子学生が実体験することで、女性研究者とは、ひいては未来の自分の姿を
具現化してもらい、博士課程進学者の増加を図ることを目的としたプログラムです。
実施日時:2016年2月17日(水)~19日(金)の2泊3日
参 加 者:山形大学工学部1名(屋代和美)、山形大学農学部2名(岡部友香、鈴木瑞穂)、米沢栄養大学1名(藤本亜紀)
訪 問 先:大日本印刷研究開発センター(千葉県柏市)、大日本印刷技術開発センター(茨城県つくば市)
【主な内容】
①大日本印刷研究開発センターの紹介(研究管理部 大野浩平部長)
②管理職講演「大日本印刷におけるダイバーシティの取組」(基盤技術開発本部 滝口理事)
③若手女性研究者との懇談会(評価解析技術研究開発本部、茨城県つくば市)
④ラボ活動の紹介(研究開発センター 自主的ワーク)
⑤管理職とのランチミーティング

|
▲参加学生全員での集合写真 |
山形大学 大学院 理工学研究科
バイオ化学工学専攻 修士1年 屋代 和美
○研究環境、設備見学で印象に残った点 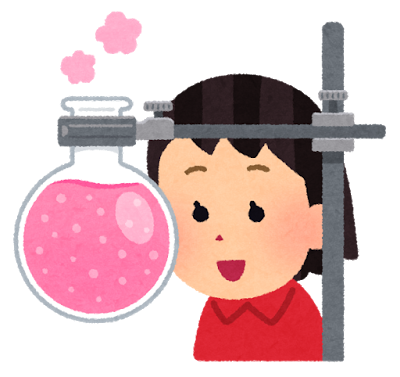
研究開発センターでは、実際に製品を見ながら会社の歴史や技術、研究環境などを教えていただきました。「印刷」と聞くと本や紙媒体をイメージしてしまいますが、大日本印刷株式会社では電子部品や壁紙などの建材も積極的に開発していると知り興味が惹かれました。
技術開発センターでは、分析室や印刷機械などを見学させていただきました。一口に印刷といっても用途によって求められる機能は様々で、それらを実現させるために社員の皆さんが日々研究を行っているということを肌で感じることができました。また、つくばでは女性研究者の方々とお話する場を設けていただきました。若手からベテランの方まで幅広く集まっていただいたので、就職活動のことや職場の環境など多くのことを質問でき、有意義な時間を過ごすことができました。
○大日本印刷株式会社におけるダイバーシティ取組みについて
D&I活動の一つとして「メンター制度」を取り入れていると説明していただきました。メンター制度とは、働く上での悩みや課題を抱えている女性(メンティ)が主体的に問題を解決するために、身近に何でも相談できる女性の先輩(メンター)を育成し、女性のキャリア形成を後押しする制度です。2013年からスタートした取り組みということで、これからDNPではさらに女性が働きやすい環境が整っていくのではないかと期待されます。
○プログラム全体を通して
3日間という短い期間でしたが、自分の想像より多くのものを得ることができました。特に、女性研究者の方々とこれほど近くで密接にお話しする機会はこれまでにない経験で、これから自分のキャリアを考える上で大変参考になりました。中には、3人のお子様がいながら正社員として長く働いている女性研究者もいらしたので、長く働きたいと思う女性には向いている会社であると思いました。
山形県立米沢栄養大学
健康栄養学部 健康栄養学科2年 藤本亜紀
2月に行われた交換留学プロジェクトには、自分が進むべき進路の手がかりや、企業というものについてなどを学びたいという思いから参加しました。
私は、2年生と3年生の間の春休み期間に参加したので、まだ自分の研究テーマなども持っておらず、進路に向けた具体的イメージは定まっていませんでしたが、今回参加して自分の将来に対する物事への見方が変わったように感じました。
三日間の中で、自分にとって最も勉強になったのは、女性研究者の方々とお話する時間でした。入社したての方や10年近く勤務されている方など、様々な年代の方がいらっしゃる中で、女性特有のライフイベント(妊娠、出産、子育てなど)の際、どのように対応されてきたのかを伺うことができました。また、女性研究者としてご自身の研究に対する想いなどをアットホームな雰囲気の中で知ることができたことは、私の中でとても印象に残っています。
今回の交換留学プロジェクトでは、女性研究者として働く方々の素敵な姿をたくさん見ることができ、とても貴重な経験となりました。 自分の視野を広く持ち、色々なことにまず興味を持つことが大事なのだと気付くことができました。
◆次年度交換留学に向けての課題◆
(参加者からのアンケートより)
・主にライフイベントを経験した女性研究者との交流であったが、ライフイベントよりも研究を選択した女性研究者とも交流がしたかった。
・女性研究者だけでなく、その周りの男性研究者との交流の機会があればより良かった。
・・・などの声があがった。
次年度では、本当の意味でのダイバーシティの観点で交流研究者の幅をより広げ、より一層充実した取組としたいと思います。
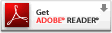 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader (無償) のインストールが必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader (無償) のインストールが必要です。