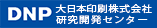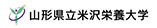| イベント | NEW!託児サポーター養成講座の受講生を募集します!※終了しました |
連携機関に所属する学生、教職員又は一般の方で、子育て支援に関心のある方を対象に託児サポーター養成講座を開催します。
講師に小児科医や保育士・栄養士・保健師・心理士等、各分野の専門家を招いて、保育の心・子どもの発育と病気・栄養と食生活・子どもの世話や遊びなど
多方面から学ぶことができます。
本講座は、子育て支援に必要な基本的な知識・技術を習得し、保育サービスを提供できる人材を養成することを目的としており、
全課程の修了者には、財団法人女性労働協会の修了証が交付されます。さらに、学生の方には、託児サポーター認定証が加えて交付されます。
託児サポーターは、連携機関が主催するイベントの際や教職員から託児(一時預かり)の要望があった場合に保育士の指導の下で幼児及び学童の託児業務(アルバイト)に携わることができます。
画像をクリックするとPDFで開きます
【日程】 ★説明会:平成28年12月12日(月)※希望者のみ
養成講座:平成29年2月13日(月)から2月17日(金)全5日間
※子育て経験のない方については、上記に加えて実習のカリキュラムを準備しております。
※詳細スケジュールについては下表でご確認ください。
【場所】 説 明 会 :山形大学工学部 4号館ゼミ室2 ※講座の場所と異なりますのでご注意ください。
養成講座:山形大学工学部 百周年記念会館セミナールーム
(山形大学工学部 所在地:〒992-8510 米沢市城南四丁目3-16)
⇒キャンパスMAPはコチラ(青字をクリックすると山形大学工学部HPにとびます)
【受講料】無料(ただし、テキスト「育児サポート3」代として2,500円が必要です)
【申込み】お申込先が分かれております
電話またはFAXでお申込みください。(山形大学においては電子メールも可)
チラシの裏面に申込書がございます。
*************申込み締切 平成29年1月30日(月)***************
連携機関に所属の学生・教職員等のお申込先
山形大学男女共同参画推進室 米沢分室 TEL:0238-26-3356/3359
FAX:0238-26-3398
Email:y-danjoyz@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
一般の方のお申込先
NPO法人やまがた育児サークルランド置賜事務所(月~金 9:00~17:00)
TEL・FAX:0238-87-0814
託児サポーター養成講座スケジュール

| イベント | NEW!自己啓発合宿の参加者を募集します!※終了しました。 |
自己啓発合宿の参加者を募集します!
女性研究者の研究開発能力、マネジメント能力、マーケティング能力の育成を目的として、ライフデザインズ・オフィス代表 小西 ひとみ氏を講師に招いて開催する自己啓発合宿の参加者を募集します。※終了いたしました。
【開 催 日】 平成28年11月29日(火) (10:30~17:30 / 18:00~ 情報交換会)
平成28年11月30日(水) (10:00~16:00)の 1泊2日
【開催場所】 31VENTURES KOIL サロン
千葉県柏市若柴178 番地4
柏の葉キャンパス148 街区2 ショップ&オフィス棟6階
*つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅西口 徒歩2分
【 講 師 】 ライフデザインズ・オフィス代表 小西 ひとみ氏
【内容概略】 チームビルディング(講義/実践)
詳細スケジュールについては別紙参照⇒実施要項およびスケジュール
【申込先】 山形大学男女共同参画推進室 米沢分室
TEL0238-26-3356・3359/FAX0238-26-3359
Email:y-danjoyz@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
| イベント | NEW!合同 シンポジウムを開催しました。 |
三機関合同シンポジウム
「女性研究者の活躍による豊かな未来の生活」
~大学・企業・地域の共同研究に向けて~
↑チラシをクリックするとPDFが開きます↑
【 日 時 】平成28年11月11日(金)13:30~16:30 ※終了しました。
【 場 所 】伝国の杜 大会議室(2F)
〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-2-1
多くの方にご参加いただき、大盛会のうちに終わりました。ありがとうございました。
シンポジウムの開催報告につきましては、コチラをご覧ください。⇒山形大学ホームページ(リンク)
【問合せ先】
山形大学男女共同参画推進室 米沢分室
電話 0238-26-3356 /0238-26-3359
| 活動報告 | NEW!英語プレゼンセミナーを開催しました! |
【開催日時・場所】
- 8月22日(月) 13:00~15:00 米沢キャンパス事務棟3階テレビ会議室
- 8月24日(水) 13:00~15:00 小白川キャンパス事務棟第一会議室
- 8月24日(水) 17:00~19:00 飯田キャンパス医学部 大学院講義室
- 8月26日(金) 13:00~15:00 鶴岡キャンパス3号館2階202講義室
【講師】
Dr.Karolin Jiptner(山形大学工学部 助教)
【内容】
・講演「これでうまくいく!英語プレゼンの進め方(How to give a great presentation in English)」
・参加者との質疑応答

【実施報告】
平成28年8月22日(月)、24日(水)、26日(金)の3日間、山形大学各キャンパスを会場として、英語プレゼンセミナーを開催しました。ダイバーシティ事業の一環として開催した本セミナーには、3機関合計で91名の参加がありました。
本セミナーの講師であるカロリン・イプトナー氏(山形大学工学部 助教)からは、英語でのアカデミックプレゼンテーションを上手に進める場合において、よく使うフレーズ、内容構成、図表の効果的な使い方についてお話しいただきました。
参加者から回収したアンケートでは、「英語の先生という立場ではなく、研究者の立場から英語プレゼンについての話が聞けて良かった。」、「話し始め方や、話題の転換などの言い回しなど、学ぶ機会がなかったので大変ためになった。」などの感想が非常に多くありました。
また、「日本語でのプレゼンにも使えることばかりなので、より多くの方(学生・職員)に参加して欲しい。」、「より多くの学生が参加できるよう、夏休み期間の開催は避けて欲しい。」といった意見もあり、対象者別の周知方法や開催時期の検討など、今後改善・考慮すべき点も明らかとなりました。
さらに、今後の希望として、「実際に数名がプレゼンをしてみるなど、講演のみでなく実践的なことを取り入れてはどうか」という意見や、「英語のコミュニケーションセミナーや、ポスターセッションについての講演、論文作成のセミナーもあれば参加したい。」など、次回開催を望む積極的な声も多数いただきました。いただいたご意見を反映して、今後も役に立つ企画を考えたいと思っております。
| 活動報告 | NEW!女性研究者 研究成果発表会を開催しました。 |
女性研究者 研究成果発表会を開催しました。

女性研究者 研究成果発表会 実施報告
日 時 : 平成28年8月7日(日) 13:30~15:00
場 所 : 山形県立米沢栄養大学 D301教室(山形県米沢市通町6-15-1)
参 加 者 数 : 47名
発 表 者 : 山形大学 工学部 産学連携准教授 泉 小波
山形県立米沢栄養大学 健康栄養学部 講師 山口 光枝
山形県立米沢栄養大学 健康栄養学部 准教授 金光 秀子
【目的】
女性研究者のキャリアパス支援の前段として、女性研究者の裾野の拡大を図ることを目的とし、高校生、大学生、地域住民等を対象とした研究成果発表会を開催するもの。
【内容】
山形大学 工学部 泉 小波 氏、山形県立米沢栄養大学 金光 秀子 氏、同大学 山口 光枝 氏の3名の女性研究者による、最新の研究成果について発表が行われた。
また、発表終了後、研究成果の公表を兼ねて研究・開発した「減塩ソーセージ」、「減塩らーめん」の試食提供が行われた。
1 開会挨拶
(山形県立米沢栄養大学 学長 鈴木 道子)
ダイバーシティとは「多様性」という意味です。多様な背景を持った研究者が研究を進めるうえで必要となる環境を整備していく事業が「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(連携型)」です。本事業は、山形大学を中心に、大日本印刷株式会社 研究開発センター、米沢栄養大学の3機関が連携して取り組んでいるものであり、文部科学省の「科学技術人材育成費補助事業」の一環として平成27年度に採択されました。
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉をよく耳にしますが、結婚や出産、育児、そして介護といったライフイベントでは、女性だけの問題ではないにせよ、とりわけ女性にかかる負担が大きくなりがちです。これにより女性研究者の研究が中断されたり、思うように進まなかったりすることがあります。こうした状況を踏まえ、本事業では、女性研究者の研究に対する支援や、准教授や教授といった上位職への就任などを支援していくことを目的としています。
他にも本事業では様々な取組みを展開していますが、そのひとつが本日開催される「女性研究者 研究成果発表会」です。この「研究成果発表会」では、研究者間の情報共有に留まらず、研究に興味を持つ高校生や大学生といった若い世代の方々が、研究の楽しさを理解する機会となればと思い開催するものです。
|
|
2 印刷と研究の話
(山形大学 工学部 有機エレクトロニクス研究センター 産学連携准教授 泉 小波)
山形大学では、ソフトブランケットグラビア印刷装置の研究をしています。印刷技術は2次元に印刷することで発展してきました。現在取り組んでいる研究テーマは、3次元への電子回路の印刷技術の開発です。1450年にグーテンベルグが活版印刷を発明しました。印刷とは単なる印刷物を発出するものではありません。聖書の印刷により、人々は書物から知識を得てきました。これは非常に重要なことです。知識を持った人々により宗教改革、ルネサンス、産業革命へと繋げられていきました。印刷技術がなければ、私達のこの豊かな生活は存在しないのです。印刷技術が発明され、進歩したことにより、現在の科学技術があるといっても過言ではありません。この印刷物に動作を与えたのがテレビです。ブラウン管テレビは1946年に日本人が発明しました。こうした技術進歩に自らも参加したいとの思いから研究者の道を選択しました。世の中には多くの研究分野があり、それに卑賤はありません。研究は必ず人の役に立ちます。研究者になるためには「意思」と「縁」が重要です。良い「縁」を作るため、礼儀、節制、節度を保ち、誰に対しても敬意の念を持って接してください。人間の生活を豊かにするのはお金ではなく科学技術です。テレビを見ることができるのはテレビを購入したからではなく、テレビを発明した人がいたからです。知識は蓄積されていきますので、自分が新しい技術に参加しようという意識を持ってください。

3 減塩ソーセージの開発と学校給食への導入の取り組み
(山形県立米沢栄養大学 講師 山口 光枝)
食塩摂取量を減らすこと、これは今多くの国民に求められている重要な課題です。食塩の取り過ぎは高血圧を招き、脳や心臓の血管の異常の原因となります。厚生労働省が毎年実施する国民栄養調査では、様々な角度からその結果を分析しています。特に、食塩摂取量に注目すると、年々徐々に低下しているものの、食品摂取基準(2015年公表)の目標値と比較した場合、依然として高い状況にあります。山形県は全国でも最も食塩摂取量の多いグループに属しており、人口10万人に対する高血圧疾患患者の割合は全国で最多となっています。米沢栄養大学では、こうした現状の改善に向け、「山形県減塩食育プロジェクト事業」を展開しています。
また、食品製造業者が食塩相当量を見直す取組みを進めることも食塩摂取量の減少に繋がります。国の減塩対策関わる専門家は、加工食品や外食などの食塩相当量を少しずつ減らしていく環境的アプローチが減塩対策に役立つと明言しています。これを踏まえ、食塩相当量の減少に向けた環境的アプローチとして、発色剤を使用しない無塩せきソーセージの生産を行っている米沢食肉公社との連携により、「減塩ソーセージ」の開発を行ってきました。その成果として、平成28年度から学校給食に導入される予定(年3回)です。
減塩の推進は、長年培った味覚や食生活に変化を求めるものでありとても難しいことです。しかし、「減塩ソーセージ」の開発にみられるように、小さな取組みの積み重ねが県民の意識改革や味覚の変化をもたらし、いずれ大きな成果となって実を結ぶ可能性があります。今後、山形県全体で減塩活動が盛り上がり、県民の健康増進につながることを期待しています。
|
|
4 「米沢らーめん」塩分濃度調査結果と「減塩醤油スープ」の開発
(山形県立米沢栄養大学 准教授 金光 秀子)
山形県は高血圧疾患患者が多く、1日当たりの食塩摂取量が全国平均の10グラムよりも多い12グラムとなっています。昨今の健康志向の高まりを受け、地元の麺業組合「米沢伍麺会」との連携により、市民の健康を意識した「米沢らーめん」の減塩醤油スープの開発を行ってきました。「米沢らーめん」は、スープを全部飲まれた場合の食塩摂取量が8グラムから12グラム程度になります。減塩スープの開発には、旨味(出汁)について、とりわけグルタミン酸、イノシン酸を含む食品の割合を考える必要があります。「米沢らーめん」はお店によって違いはありますが、鶏ガラ出汁、醤油をベースにしており、鶏ガラ出汁にはグルタミン酸が含まれております(煮干し出汁にはイノシン酸が含まれています)。グルタミン酸ナトリウムとイノシン酸ナトリウムの配合割合は、半々くらいで最も相乗効果が高くなります。これらを踏まえ、「減塩醤油スープ」の開発に向け、年齢別のアンケート調査を実施した結果、塩分濃度は0.8パーセント、量は器の形状も加味しながら400ミリリットルが適しているとの結論に至りました。開発された「減塩醤油スープ」は一袋約32グラムで、これを300ミリリットルの熱湯で希釈するというもので、通常のスープと比較して56パーセントの減塩となります(らーめん全体としては40~50パーセントの減塩)。スープを飲み干してもらうことが美味しさの評価と考えているお店と、美味しいが健康のためスープは残したいというお客さんのコミュニケーション不足を解消するため、「米沢らーめんから始める元気なまちづくり」という組織では、米沢市内の20軒のお店で適塩行動の「のぼり旗」、「カード」を設置し、お店とお客の健康増進に向けた意思疎通を図っています。
|
|
5 試食提供:「減塩らーめん」と「減塩ソーセージ」の試食
「研究成果発表会」終了後、「減塩らーめん」と「減塩ソーセージ」の試食が行われた。「減塩らーめん」、「減塩ソーセージ」ともに、塩分濃度を抑えただけではなく、旨みや風味が十分引き出されており、想像以上にしっかりとした味付けとなっており、試食会への参加者からも「とても美味しかった」と好評を得たところである。
|
|
|