

この度は、山形大学男女共同参画及びダイバーシティ推進賞を賜り、大変光栄に存じます。私がこのような賞をいただくことができたのは、学部の垣根を越えて多くの方々のご指導とご協力に恵まれたおかげであり、支えてくださった皆様に心から感謝申し上げます。
私はこれまで、小中高生向けのサイエンス教育や、学生・若手研究者へのキャリア支援、留学生と市民の交流会など多様な活動を通じて、多くの方々と関わる機会を得てきました。また、研究者としての経験や、研究と育児の両立についてメディアを通してお話しする機会も多くいただきました。
これらの経験を通じて、ダイバーシティの重要性を改めて認識するとともに、この地域社会にはまだ多くの課題が残されていることを痛感しています。ダイバーシティの推進の本質は、単に人種や性別などのバランスあわせといった形式的な取り組みではありません。全ての人が、一個人として尊重される世の中を実現することにあります。マジョリティ側の特権の自覚を促し、互いの違いを価値として認め合う文化の醸成が必要です。この賞の存在は、私たちが理想とする社会に到達していないことを示唆しています。だからこそ、私は将来的にこの賞が不要となる社会、つまり多様性が自然に受け入れられる社会を実現するために今後も尽力してまいります。
河合寿子氏は、“全ての人が生きやすい山形”の実現に向けて学内外で多様な活動を継続し、男女共同参画及びダイバーシティに対する意識の醸成に大きく貢献してきた。
学内ではヤマガタ夢☆未来Girlsプロジェクト、地域共創STEAM教育推進センター、ダイバーシティ推進室、JSPSひらめき☆ときめきサイエンスなどの活動の中で、とくに理系分野に進む女性の増加をめざし、学外では小中高校に加え公民館等の公共施設にも出向き、サイエンスを楽しむ豊かな心を育てる活動を行っている。また、女子中高生やその保護者との対談を通して理系という生き方について理解を深めてもらえるよう務めてきた。さらに、近年は多くのメディアでロールモデルとしての姿が取り上げられている。
また、研究においては、2023年度に開催された女性研究者によるシンポジウム「光合成研究とワークライフバランス」において招待講演を行う等、複数の学術講演等の機会を得て、多くの演者・パネリストを務めてきた。
以上の通り、河合寿子氏は、学内外における理系分野に進む女性の裾野拡大に向けた支援活動を行い、女性研究者としても全国的な学術講演等で自身の研究成果とともにダイバーシティ推進の意義を積極的に発信し、継続的に活動を続けてきたことを高く評価し、令和6年度の受賞者に決定した。


今回、このような素晴らしい賞を受賞できたことを誇りに思います。
私が学生だった頃は、基礎研究分野で活躍する女性研究者に出会えることはめったにありませんでした。子供のころから勉強が好きで、気づいたら実験をしたい、研究者になりたいと思っていましたが、ロールモデルもなく、手探りでここまで来ました。現在は、女性が活躍できるようにポジティブアクションがとられ、大きな良い変化を感じます。
どんなことでも、大きな変化があれば、ひずみも出で来るでしょうし、何が正解かはわかりません。この世界で生きる我々は、考え続け、模索しながらより良い世界・社会に変化し続けることを期待して生きていくしかないのだと思います。微力ながら、これからも男女共同参画・ダイバーシティ推進にかかわっていきたいと思います。男女共同参画・ダイバーシティ推進という言葉がなくなる日まで。
黒谷玲子氏は、2010年に本学初のテニュアトラックの女性教員として採用された後、2016年に本学初の国際ソロプチミスト山形クラブ賞を受賞するなど、数多くの賞を受賞している。
学外においては、長年に渡って男女共同参画推進に努め、所属する2つの学会において、それぞれ委員を務め、学会におけるダイバーシティ推進の企画運営や託児室の設置運営を行う等、学会における男女共同参画推進に大きく貢献している。加えて、講演や学会発表においても活躍して、2021年に米沢興譲館高等学校において講演した際には各方面で報道された。
学内においては、積極的にセミナーを開催し、国内外の最新の研究や企業での研究について、教職員から学生まで広く学ぶ環境作りをしている。ダイバーシティ推進室における事業においても、基盤教育科目での講義の担当や、広報事業への寄稿を行っている。また、複数のシンポジウムでの発表や、女性研究者裾野セミナーを複数回開催する等、本学での理系研究の魅力を継続して発信している。
以上の通り、黒谷玲子氏は、質量ともに豊富な研究実績を有し、多くの科研費や競争的資金を獲得しており、本学の優れた女性研究者の姿を示すとともに、女性研究者のキャリア形成に関して、国際的な活動も含め学内外において継続的に活動を展開してきたことを高く評価し、令和6年度の受賞者に決定した。
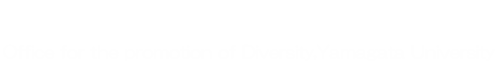

推進室について
支援制度
お知らせ
推進室の取組み
刊行物
お問い合わせ